
電動menu
◆ 壊れにくい飛行機で3Dアクロの練習がしたくて、電動を始めるにはいくらかかるか調べました。
◆ 壊れにくい飛行機で3Dアクロの練習がしたくて、DuplexEPPで、電動を始めちゃいました。
◆ Li-Poバッテリーは、取り扱いに注意しましょう!
◆ 電動2機目、ZequeEPPを作っちゃいました。
◆ 電動3機目で、バルサ機 mini Extra 330L です。これでできたら、トルクロール卒業です。
◆ 特別な測定器がなくても、Li-Poバッテリーの残量を知る方法。
壊れにくい飛行機で3Dアクロの練習がしたいけど、 たっかいねぇ〜!!
始めるとしたらいくらかかるのか? 調べてみました。
合計 \ 76,734
R146iP
チャンプ \6,800 + \1,050 = \7,850
若林模型 \5,999 + \1,222 = \7,221
高崎ラジコン \10,500 * 0.8 = \8,400
Li-Poバッテリーは、取り扱いに注意しましょう!
→正式名称は、リチウムイオンポリマーバッテリーです。
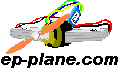 ←電動飛行機に関する知識はここで勉強しよう!
←電動飛行機に関する知識はここで勉強しよう!
LiPoバッテリーの安全に対する意識が強く、おすすめ!
最新情報はここ
 Air Craft データページ
Air Craft データページ
リチウムポリマー電池の充電、取り扱いと安全についての情報
 Lipoの危険性について
Lipoの危険性について
Duplex EPP 製作、飛行レポート
| 製作編 |
| 1.買っちゃいました。 |
|
 |
上の表の通り、部品を買っちゃいました。
お金かかるねー。 |
|
 |
残念なことに、アンプのコネクターが破損していました。
クレームで処理するのも面倒なので自分で直そうと思います。
また、アエークラフフトじゃないものにはBECスイッチは付かないようです。 |
|
 |
LiPoを安全に保管するために、”瓶”を買いました。
これなら万が一発火しても大丈夫! かな? |
|
 |
機体、入荷しました。
ぱっと見、綺麗ですが、かなり雑なEPPでできていて表面はボロボロです。
少しがっかりです。 |
|
 |
受信機は、佐野の若林模型まで足をのばして買ってきました。
ノイズの多い電動にはPCM受信器が必須ですよ! |
| 2.ベンチテスト |
|
 |
部品が揃ったので安定化電源でベンチテストを行いました。
モーター:HYPERION 2213-24
プロペラ:GWS スローフライ 10x4.7
電源電圧:11.1V
最大電流:15A
最大電力:160W
最高回転:6,900rpm
制止推力:930g
推力は充分です。
少々オーバーロード気味ですが、ほとんど全開にする必要がなさそうなので
大丈夫でしょう。
|
| 3.動翼にテープ貼り |
|
 |
説明書、読みました。
製作が、思っていたよりずっとめんどくさそうです。
ほとんど完成機だし、もっと簡単に作れると思っていました。
まず、動翼にクリアテープを貼ります。
テープの付きを良くするために全面にスプレーのりを吹きます。 |
|
 |
次に、クリアーテープを貼ります。
まるでフィルム貼りです。面倒です。疲れますので休み休みの作業です。
→後で、分かったのですが、クリアーテープは相当強力なものじゃないと
テープが浮いてきてしまいます。テープもRC-HOBBYで買っておけば良
かったと思いました。 |
|
 |
なんとか、テープ貼り終わりました。
張り方は、適当です。
説明書には詳しい作り方がかいてありません。
初めてだとかなり厳しいですね。 |
| 4.カーボン貼り付け |
|
 |
胴体と主翼をカーボンで補強するのですが、付属しているカーボンのクオリティ
が低いです。繊維がボロボロはがれかけているし、切断面が盛り上がっていて
平らじゃありません。
貼り付ける前に紙ヤスリで均しました。 |
|
 |
カーボンの張り方も説明書に書いてありませんが、なんとか貼りました。
主翼のカーボンはゼリー状瞬間で貼って、グラステープでカバーしましたが、
胴体のはスコッチのプラスチック用接着剤で貼りました。
結果、スコッチの接着剤で貼った方が良かったようです。
貼り終わって気づいたのですが、主翼のカーボンが説明書の写真よりかなり
長いです。切るべきだったのか?不明です。 |
| 5.主翼接合 |
|
 |
ラダーサーボとエレベータサーボを取り付けて、主翼を接合しました。
サーボはきつかったので接着せず、差し込んで、グラステープで抜けないように
押さえるだけにしました。
主翼は、EPPなので、位置や角度を出すのが非常に大変です。
また、胴体がねじれていたため主翼の角度をどこに合わせたらいいのやら、
まあ、飛べばいいやということで、適当に合わせて、スコッチの接着剤で接合部
を固めました。 |
| 6.動翼取り付け |
|
 |
ラダーとエレベータを取り付けました。
EPPなのでちょっとした力の入れ具合で変形してしまうので、左右のエレベータの
水平を出すのが非常に大変でした。
何度も何度もやり直したため汚くなってしまいました。悲しいです。
ヒンジを何で接着すればいいのか、説明書に書いてないので困りました。 |
|
 |
エルロンを取り付けました。
ヒンジは瞬間接着剤と硬化促進剤で接着しました。大丈夫かな?
ラダーとエルロンはスムーズに蛇角が取れるように、固定翌側の角をはさみで
カットしてから取り付けました。 |
| 7.ギア |
|
 |
テールギアはバルサで作りました。
はじめ、ピアノ線で作ったのですが、相手がEPPなのでしっかり固定できません
でしたので、バルサで作り直しました。 |
|
 |
メインギアを取り付けました。
説明書では胴体を切り裂いて取り付け、取り付け後切り口を接着せよとなってい
ましたが、私は左右のピアノ線の出る位置に水平に15mm程度の切り込みを入れ
てピアノ線を差し込んで通しました。
また、せっかくスパッツが付いているので取り付けました。 |
| 8.マジックテープ |
|
 |
受信器を積んで、胴体上部の開口部にマジックテープを貼りました。
マジックテープは付属の物では足りないのでダイソーで買い足しました。
半分に切って使用しました。 |
|
 |
下部は、バッテリーの搭載を行います。
重心を確認するとメインギアをまたいでバッテリーを搭載しなければならないため
補修用のEPPを貼ってかさ上げしました。接着にはやはりスコッチの接着剤が最
適の様です。
バッテリー搭載用のマジックテープも接着剤を塗って硬化したところに貼ると強力
に貼り付きます。
付属のファスナー様のマジックテープは初めから細く切ってあるので注意してくだ
さい。 |
| 9.完成 |
|
 |
とりあえず、飛行可能な状態になりました。
重さは、354g(機体)+104g(バッテリー)=458g となりました。
推力の約半分の重さです。 |
その他の購入品
| 名称 |
写真 |
用途/インプレッション |
購入価格 |
| 自動車用バッテリー |
 |
LiPo充電用、親電源
インジケーターで電解液の比重が確認できるので充電器の
親電源にはもってこいです。
充電はEOS7iやシュルツでオートカットで充電できます。
その場合、12V10A程度の直流電源装置が必要になります。 |
\1,980 |
| アルミケース |
 |
充電器等収納/携帯用ケース
小物入れと、クッションを兼ねて、フタ側にはダイソーで買った
ソフトケースをマジックテープで付けました。
マジックテープはスコッチのプラスチック用接着剤を塗って貼り
付ければバッチリです。 |
\1,980 |
飛ばしちゃいました(動画)
 練習になります!他のEPPファンフライ機とはひと味違うと思います。簡単にトルクロールできません。難しいので練習になります。失速時の操縦感覚はバルサの機体とほとんど変わりません。 練習になります!他のEPPファンフライ機とはひと味違うと思います。簡単にトルクロールできません。難しいので練習になります。失速時の操縦感覚はバルサの機体とほとんど変わりません。
機体の表面抵抗が大きいのか、ブレーキがよくききますが、パワーをかければ多少風があってもちゃんと上空飛行できます。LiPo、1200mA-3S(11.1V)で機体重量の約2倍の推力があるので十分なパワーです。
何度か落ちて、胴体がくの字に曲がりましたが、破損しませんでした。ピッチングして頭から落ちたときにエレベータのサーボギアが欠けたり、トルクロールでラダーをついてしまい、ラダーのサーボギアが欠けたりしましたが、破損はその程度で、さすがにEPPは丈夫です。パワーがあるのでサーボは金属ギアにしておけば良かったかも知れません。
飛行時間は、1200mAで15分程度と、充分です。LiPoの充電時間はEOS7iで、充電電流1Aで、85分ほどかかります。容量28Ahの自動車用バッテリーを親電源にして、6回程度充電すると、自動車用バッテリーのインジケータが白に変わりました。自動車用バッテリーは、シュルツ等のコンピュータ充電器を使ってフルオート充電できます。最大充電電流5Aで、満充電になるまでに3時間程度かかりました。鉛バッテリーは使ったら直ぐに、こまめに充電して、常に満タンにしておくのが長持ちさせるコツだそうです。
スロットルの操作フィーリングをエンジンに近づけるために、スロットルカーブを使用し、スロー側の立ち上がりが早くなるように調整しました。 |
その後
 LiPoバッテリー保管壺の底に仲間からもらった砂利を敷きました。 LiPoバッテリー保管壺の底に仲間からもらった砂利を敷きました。
これで発火しても安心? 砂利はよく洗ってから引きました。
他に、LiPoバッテリーの保管に、コンクリートブロックを利用するのも良い案だと気づきました。
コンクリートブロックの穴に1つずつバッテリーを保管すれば発火しても被害は最小限で済むでしょう。しかも安い!これが決定版かも知れませんね。 |
 結局、金属ギアサーボを買っちゃいました。 結局、金属ギアサーボを買っちゃいました。
とりあえず、ラダーとエレベータのサーボを変更しました。
これで、墜落しても大丈夫!? |
更にその後
 その後、殆ど飛ばす日には1回は墜落して、もう10回以上は墜落していると思いますが、おかげさまでサーボは大丈夫です。 その後、殆ど飛ばす日には1回は墜落して、もう10回以上は墜落していると思いますが、おかげさまでサーボは大丈夫です。
左の写真は木に引っかかって枝で主翼が裂けてしまった様子です。これは今までで最大の破損です。直るか心配でしたが、スコッチのプラスチック用接着剤でなんとかなりました。
一応まだ飛んでいますが、落ちて変形したところはEPPが柔らかくなるので、機体はどんどんふにゃふにゃになってきています。1年持つかどうかと思っています。 |
 現在の飛行はこんな感じです。 現在の飛行はこんな感じです。
でもこのEPPの機体を飛ばすようになってからトルクロールがかなり上手くなったのは確かです。
もう一つ分かったことは、やっぱり電動も夏は厳しいということです。バッテリーもモーターもアッチッチです。取り扱いには注意しましょう。
|
 これは、おすすめ! これは、おすすめ!
LiPoを4本同時に充電できる充電器、"PolyCharge4"を購入しました。1台でバッテリーが4本同時に充電できるのは、"いい"です。
これがあれば、じゃんじゃん飛ばせます。 |
遂に2機目だ! ”Zeque EPP Acro”
メカは全部Duplexから移植するつもりで、機体のみ購入しました。 \17,800です。 高いねぇ。
 1機目のEPP機"Duplex"が、半年で、予想外にボロボロになってきてしまいました。まあ、20回以上も墜落すれば当然なのですが、よく頑張ってくれました。それと、"Duplex"にはかなり慣れてしまったので、もう少し難しい機体が欲しくなりました。 1機目のEPP機"Duplex"が、半年で、予想外にボロボロになってきてしまいました。まあ、20回以上も墜落すれば当然なのですが、よく頑張ってくれました。それと、"Duplex"にはかなり慣れてしまったので、もう少し難しい機体が欲しくなりました。
で、タイミング良く、”Zeque EPP Acro"が発売になるというので、予約しておいたのですが、遂に入荷しました。 |
 主翼や動翼、胴体など、全てカーボン内蔵で補強済みです。かなりしっかりしています。その代わり墜落したらダメージも大きそうです。 主翼や動翼、胴体など、全てカーボン内蔵で補強済みです。かなりしっかりしています。その代わり墜落したらダメージも大きそうです。
主翼には2本x上下面の4本、エルロンにも1本x上下面の2本のカーボンが入っています。 |
 胴体には1本x左右の2本が、機首から尾翼まで貫通してカーボンが入っています。 胴体には1本x左右の2本が、機首から尾翼まで貫通してカーボンが入っています。 |
 では、製作開始です。 では、製作開始です。
例によって、動翼を梱包テープで補強しますので、スプレーのりを吹きかけました。
Duplexでは、後で梱包テープがはがれてきたので、今回はたっぷり吹きました。
これで、Duplexで買った100ml缶が終わりました。
|
 今回は、テープはRC-Hobbyで買った、Office DEPOTのテープです。 今回は、テープはRC-Hobbyで買った、Office DEPOTのテープです。
やっぱりテープ貼りが一番めんどくさいです。 |
 次に、主翼をはめ込みました。 次に、主翼をはめ込みました。
前縁部に隙間ができます。EPPを三日月状に切って隙間を埋めました。
Zequeの加工は精度が良く、差し込んだだけで直角が出ました。 |
 左右のバランスを確認し、スコッチのプラスチック用接着剤を流して接着します。 左右のバランスを確認し、スコッチのプラスチック用接着剤を流して接着します。
この辺は、Duplexで何度も修理しているので、接着剤の扱いに馴れてきている感じです。 |
 水平尾翼を取り付けました。 水平尾翼を取り付けました。
接着部分の梱包テープはカットして剥がします。
エレベータの動きを阻害するので、水平尾翼センターの前縁を少しカットしました。 |
 各動翼にヒンジを取り付けました。 各動翼にヒンジを取り付けました。
カッターで切り込みを入れて、ヒンジを差し込みます。
ヒンジを曲げ、隙間を広げながら、瞬間接着剤を奥までたっぷり流し込みます。
その後、硬化促進剤で固めます。 |
   動翼を接着しました。 動翼を接着しました。
カッターでヒンジの切り込みを入れ、差し込んで、瞬間接着剤を流し込み、硬化促進剤で固めました。 |
  Zeque EPP にはベニヤのサーボベッドが付属しています。Futaba用とWaypoint用の2種類が付いていますが、ザイズが合わなかったので穴を修正し、瞬間接着剤と硬化促進剤で貼り付けました。 Zeque EPP にはベニヤのサーボベッドが付属しています。Futaba用とWaypoint用の2種類が付いていますが、ザイズが合わなかったので穴を修正し、瞬間接着剤と硬化促進剤で貼り付けました。
機体上部が開いているのでサーボの配線を通すのは楽々ですが、後で接着して閉じるのが大変そうです。 |
  エレベータホーンを取り付けました。説明書ではホーンのピンをカットしてカーボンかんざしに瞬間接着剤で貼り付けよ、となっていましたが、強度が不安だったのでカーボンに穴をあけ、ピンを差し込んで接着しました。 エレベータホーンを取り付けました。説明書ではホーンのピンをカットしてカーボンかんざしに瞬間接着剤で貼り付けよ、となっていましたが、強度が不安だったのでカーボンに穴をあけ、ピンを差し込んで接着しました。 |
 テールギアは、標準ではピアノ線ですが、工作が難しそうだし、重そうだし、強度も疑問だったので、Duplexで行ったバルサ板方式にしました。 テールギアは、標準ではピアノ線ですが、工作が難しそうだし、重そうだし、強度も疑問だったので、Duplexで行ったバルサ板方式にしました。
Acroバージョンでは、ラダーのリンケージを工夫しないと、エレベータに干渉してしまいます。説明書はF3Aバージョンで書かれていますのでこのことは触れられていません。注意してください。 |
 メインギアはバルサ板と共に切り込みに差し込んで接着します。 メインギアはバルサ板と共に切り込みに差し込んで接着します。
切り込みが狭いのでそのまま押し込むとEPPが裂けます。 |
 エルロンのサーボ穴はEPPでしっかりできていて、近くをカーボンが通っているので、ベニヤのサーボベッドは使いませんでした。 エルロンのサーボ穴はEPPでしっかりできていて、近くをカーボンが通っているので、ベニヤのサーボベッドは使いませんでした。 |
 マジックファスナーを貼り付けました。 マジックファスナーを貼り付けました。
背中を閉じる前に作業した方がやりやすいです。
マジックテープを貼る位置には、あらかじめスコッチのプラスチック接着剤を塗って、乾かしておきます。 |
 背中を閉じました。 背中を閉じました。
真っ直ぐできたかどうかは???
クリップで挟んだ部分が縮んでしまいました。 |
 モーターマウントを接着し、モーターを取り付けました。 モーターマウントを接着し、モーターを取り付けました。
バッテリー固定用のマジックテープは重心位置を確認してから最後に貼り付けます。マジックテープは、スコッチのプラスチック用接着剤を塗り、乾いてから貼ります。
3セル、1200mAhのバッテリーを載せたのでできる限り前に搭載しても未だ重心が後ろ気味です。1500mAhのバッテリーが必要なようです。 |
 アンプは機体下部に搭載します。 アンプは機体下部に搭載します。
搭載位置にカッターで穴をあけます。穴の縁は付属のEPP材で補強します。
アンプは胴体内の隔壁を一旦切り、そこから通しました。アンプを通した後、切った部分にEPPを接着しました。 |
 受信機を搭載しました。 受信機を搭載しました。
マジックテープは、スコッチのプラスチック用接着剤を塗り、乾いてから貼ります。
完成重量は、バッテリー無しで、436g、バッテリー込みの全備重量は、539gとなりました。 |
 完成しました。無事に初飛行を終えました。 完成しました。無事に初飛行を終えました。
飛びは,Duplexとは全然違います。ふわふわした感じはなく、飛行機としてちゃんと飛びます。ねらい通り、トルクロールが、より難しくなりました。これで、よりバルサ機に近い感覚で練習できそうです。エレベータとラダーの蛇角はあまりつけすぎない方が良さそうです。
ダウンスラストの指定は0°だったのにダウンスラストが付いていたのと、サイドスラストも強すぎる感じだったのでスペーサーを入れて修正しました。 |
その後
     |
| ZequeEPPに使用されているEPP素材は、DuplexEPPのものより堅いです。なので、機体がしっかりしていて飛行機らしくしっかり飛びます。そのかわり、墜落するともろくて、よく割れます。ナイフエッジやロールに失敗して横から落ちると主翼後部の胴体に強いストレスがかかります。内部がカーボンで補強されていますが、何度か折れ曲がると披露で切れてしまいます。製作時点で、上部内側からこの部分を補強しておくことをお勧めします。グラステープを貼っておくと良いと思います。また、機首部分もグラステープで補強しておくことをお勧めします。頑張って直しました。EPPの機体は、ボロボロになってもスコッチの接着剤があれば、頑張れば直せるのがすばらしいですね。 |
mini Extra 330L これで、トルクロールができれば、トルクロールは卒業だ!
電動飛行機、3機目で、あえて小型バルサ機。挙動が早くて、3Dアクロは非常に難しい!
 モーターは、いろいろ悩んで HIPERION 2213-20 を選びました。 モーターは、いろいろ悩んで HIPERION 2213-20 を選びました。
軽量でパワーがあるのはこれしかない様です。
最初、安価な同クラスのモーターを使ってみましたが、もう一歩パワー不足でした。
特に挙動がクイックな小型バルサ機では、姿勢を立て直すためにモーターに瞬発力が必要です。この機体は、エンジンと電動兼用ですが、エンジンにするつもりはないので、マウント部分のベニヤを肉抜きして軽量化しました。 |
 アンプは機首部側壁にマジックテープで固定しました。 アンプは機首部側壁にマジックテープで固定しました。
メインギアはベニアにビス止めですが、がっちり固定してしまうと着陸でベニヤが破損しそうなので、EPPを挟んで、柔軟性を持たせつつ取り付けました。
メインギアは、取付前にいくつか穴をあけ軽量化しました。 |
 バッテリーマウントを取り付けました。 バッテリーマウントを取り付けました。
説明書には取付方法が書いてないので、戸惑います。また、説明書では、主翼を外してバッテリーの交換とコネクターの接続を行うようになっています。面倒に思いましたが、追加工を行うと重量が増加してしまうので、説明書通りの方法を選びました。
バランス的に機首部が軽いので、バッテリーをできる限り前に積めるようにマウントを取り付けました。マウントはバッテリーサイズに合わせて軽量化しました。 |
 受信器はFutabaのPCM1024、R146iPを付けました。 受信器はFutabaのPCM1024、R146iPを付けました。
軽量化のためケースを外してあります。
最初、出費を抑えるために、GWSのFM_6chを使いましたが、FM受信器はどうしてもノイズにより誤動作してしまいます。大蛇角の小型アクロ機ではそれが命取りになってしまいますので、高価ですが、PCMに切り替えました。 |
 キャノピーは切り取り線が入っていないので、加工が少し大変です。 キャノピーは切り取り線が入っていないので、加工が少し大変です。
テープでラインを出し、テープに沿って切りました。
軽量化のため、取付は両面テープで、嵌め殺しです。 |
 バッテリー(HIPERION 3S 1500mAh)を積んで、重量687gとなりました。 バッテリー(HIPERION 3S 1500mAh)を積んで、重量687gとなりました。
写真は、一度墜落して修復した後なので、カウルに傷があり、ラダー上部の色が違っています。
軽量化のためにステッカー類は貼っていません。 |
かなり手強いですが、頑張れば、なんとかトルクロールできそうです。
風がなく、心身共に充実いているときにチャレンジします。
Li-Poの残量を知りたい →電圧を測ればだいたい残量が分かります。
Celmeterというものが発売されて、LiPoバッテリーの残量なんかが気になりだして、
結局バッテリーの残量はLiPoの開放電圧で予測しているんですよね。
CelMeterがなくても、液晶表示付きの充電器ならだいたいバッテリーの電圧が測れるように
なっていますから、飛行後や充電後にバッテリーの電圧を測って、バッテリーの状態を
把握することができますよ。
LiPoの開放電圧と、だいたいのバッテリー残量表
| 残量(%) |
1セル |
2セル |
3セル |
4セル |
5セル |
| 100% |
4.17v |
8.33v |
12.50v |
16.67v |
20.83v |
| 90% |
4.12v |
8.23v |
12.35v |
16.47v |
20.58v |
| 80% |
4.07v |
8.13v |
12.20v |
16.27v |
20.33v |
| 70% |
4.02v |
8.03v |
12.05v |
16.07v |
20.08v |
| 60% |
3.97v |
7.93v |
11.90v |
15.87v |
19.83v |
| 50% |
3.92v |
7.83v |
11.75v |
15.67v |
19.58v |
| 40% |
3.87v |
7.73v |
11.60v |
15.47v |
19.33v |
| 30% |
3.82v |
7.63v |
11.45v |
15.27v |
19.08v |
| 20% |
3.77v |
7.53v |
11.30v |
15.07v |
18.83v |
| 10% |
3.72v |
7.43v |
11.15v |
14.87v |
18.58v |
| 0% |
3.67v |
7.33v |
11.00v |
14.67v |
18.33v |
HYPERIONアンプのLiPoのカット電圧は、初期設定が2.8v/セルに設定されていますが、
バッテリーにとっては過放電ギリギリで、低すぎるようです。
3.0v/セル程度に設定することをお勧めします。
満充電後の電圧を測定することで、バッテリーの劣化状態が把握できます。
バッテリーが劣化してくると、満充電後の電圧が下がってきます。
良好なバッテリーは、満充電後の電圧は、12.5v前後ありますが、劣化してくるとその電圧が
12.45〜12.35vと低くなってきます。
膨れていないのでそのまま使っていますが、瞬発力と持続力が落ちているのが感じられます。
バランスなどに充分注意しながら使う必要があるますね。
















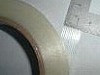
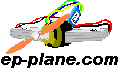 ←電動飛行機に関する知識はここで勉強しよう!
←電動飛行機に関する知識はここで勉強しよう! Air Craft データページ
Air Craft データページ